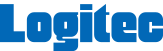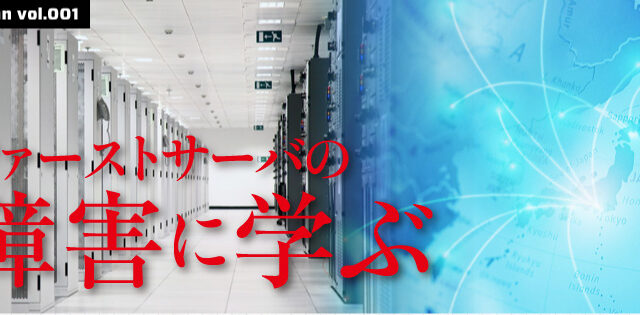Webサイトの運用に使われているサーバーが、サイバー攻撃の被害に遭う事態が増加しています。サイト運用の肝ともいえるサーバーが被害を受けると、サービスの提供や業務に多大な支障が出るため、セキュリティー対策を行うことが大切です。
ここでは、サーバーセキュリティーの重要性や主な対策方法をご紹介します。
1 サーバーセキュリティーが重要な理由

現代の企業活動において、サーバーは欠かせないものとなりました。自社サイトの運営や顧客情報の管理など、さまざまな場面で企業サーバーは活用されています。
しかし、重要な情報が保存されているサーバーは攻撃の標的になりやすい点に注意が必要です。実際に不正アクセスをはじめとしたサイバーセキュリティー上の脅威は増加傾向にあります。※1
セキュリティー対策を怠った結果、不正アクセスによる情報漏えいやサイトの改ざん、サーバーダウンなどの問題が発生すると、社会的信用の失墜や損害賠償、国から行政指導を受けるといった事態につながりかねません。
サイバー攻撃によるリスクを低減し、サーバーの可用性や機密性、完全性を確保するためにも、サーバーセキュリティー対策を適切に行うことが重要です。
2 どんなサーバーが狙われやすい?

サーバーと一口にいっても、機能や役割から「Webサーバー」や「APサーバー」「DBサーバー」「ファイルサーバー」など、さまざまな種類に分けられます。
中でも注意したいのが、Webサイトに関連するサーバーです。Webサイトはインターネット上で公開されているので、サイバー攻撃を仕掛けるために狙われやすい傾向にあります。
ただし、Webサイトに関連しないサーバーだからといって、サイバー攻撃のリスクがゼロなわけではありません。
3 サーバーを狙うサイバー攻撃の手法は2つ

サーバーを狙ったサイバー攻撃は、大きく標的型攻撃と無差別型攻撃に分けられます。サーバーセキュリティーを強化するには、主な攻撃の手法や目的を知ることも大切です。
3-1 標的型攻撃
標的型攻撃とは、特定の個人や組織を狙って行うサイバー攻撃のことです。嫌がらせや機密情報の取得、金銭の要求などが目的に挙げられます。
大量アクセスによって負荷をかけることでサーバーをダウンさせる(DDoS攻撃)、機密情報を盗み取る、サイト内容の改ざんなどが、主な被害の例です。
企業・個人に関わらず、誰でもサイバー攻撃の標的にされる恐れがあります。
3-2 無差別型攻撃
特定の個人や組織ではなく、メールやWebサイトなどを使って不特定多数に攻撃を仕掛けるのが無差別攻撃です。嫌がらせや詐欺、クラッキング(ハッキング)技術を見せつけることなどを目的に行われます。
機密情報や個人情報が漏えいする、データを暗号化されて使えなくなる(ランサムウェア)、個人アカウントを不正利用されるなどが、無差別型攻撃の主な被害です。
4 サイバー攻撃で想定される被害

サーバーのセキュリティー対策が不十分だと、どのような被害が発生するのでしょうか。
ここでは、サイバー攻撃によって想定される被害やリスクをご紹介します。
4-1 データの紛失や流出
サーバーの脆弱性(セキュリティーホール)を突かれてサイバー攻撃を許すと、サーバー内のデータが紛失したり、流出したりする恐れがあります。標的になりやすいのは、企業内の機密情報や、顧客・取引先の名前、住所といった個人情報です。
盗まれたデータは、不正に利用されるリスクもあります。
4-2 データの改ざんや乗っ取り
サーバーの脆弱性を突いて、内部データの改ざんやアカウントの乗っ取りが発生する恐れもあります。データ改ざん・乗っ取りの原因としては、管理者のパソコンのウイルス感染や、アカウント情報の流出などが挙げられます。
4-3 サービスの停止
DDoS攻撃などによって短時間で大量のデータが送られると、大きな負荷が原因でサーバーがダウンしてしまう恐れがあります。
サーバーがダウンしている間は、そのサーバーに関連するサービスも使うことができません。
サービスを提供できないことによる金銭的な損失はもちろん、サーバー復旧のためのコストも発生します。
4-4 マルウェア感染や不正行為の踏み台
悪意あるマルウェアに感染し、サーバーに保存してあったデータが使えなくなり、業務に大きな影響を及ぼすことも考えられます。
他にも、外部から不正操作を行えるウイルスに感染し、他のシステムに攻撃を仕掛けるための踏み台として使われる恐れがある点にも注意が必要です。
サイバー攻撃の加害者と疑われ、社会的な信用が落ちてしまうこともあります。
5 サーバーセキュリティー対策の具体例

サーバーへの攻撃を防ぐためには、どのようなセキュリティー対策を行えば良いのでしょうか。
ここでは、サーバーセキュリティーの対策例をご紹介します。
5-1 管理者権限を持つユーザーIDの変更
アカウント情報の適切な管理は、セキュリティー対策の基本です。特に、管理者権限を持つアカウントはサーバーに対する全ての操作を行えるため、不正利用されると大きな被害につながる恐れがあります。
管理者権限のアカウントのユーザーIDは「Administrator」で統一されていることが一般的です。その状態だとパスワードを推測するだけで不正アクセスできてしまうため、サイバー攻撃を受けるリスクが高まります。 サーバーの設定画面から、ユーザーIDは必ず変更しておきましょう。
5-2 悟られにくいパスワードの設定
サイバー攻撃のリスクを下げるには、パスワードを複雑で簡単に推測できないものにすることも重要です。
例えば、固有名詞や名前、「1234」「abcd」といった簡単なパスワードだと、考えられる組み合わせを全て試す「ブルートフォース攻撃(総当たり攻撃)」で見破られる可能性が高まります。
次の方法を心がけ予測されにくく安全性の高い、複雑で長いものを登録するようにしましょう。
【推測されにくいパスワードの設定方法】
・桁数を増やす
・数字とアルファベット、記号など、異なる文字を組み合わせる
・固有名詞や誕生日のように、意味を持つ文字列は避ける
・シンプルな文字(1234、abcdなど)は使わない
ただし、複雑なパスワードを登録したとしても、さまざまな場所で使い回していると、流出のリスクが高まります。パスワードの使い回しは控えて、適切に管理することを心がけましょう。
セキュリティーを高めるために、ワンタイムパスワードを活用するのもおすすめです。
5-3 アクセス権限の設定
サーバー内のローカルファイルに対して、アクセス権限を設定しておくことも大切です。アクセス可能なユーザーを制限することで、セキュリティーレベルの向上を図れます。
データの閲覧のみ可能、編集や書き込みも行えるなど、アクセス権は細かく設定できるため、ユーザーごとに必要な権限を適切に許可することもおすすめです。
5-4 使わないアカウントの削除
現在は使用していない、使用頻度が極端に低いといったアカウントは削除しましょう。放置していたアカウントを悪用された結果、情報漏えいやデータの改ざんなどが発生する恐れがあります。
また、退職した社員がサーバーに不正にアクセスして機密情報を入手することも考えられます。退職した人のアカウントや、テスト用に設定したアカウントなど、必要なくなったアカウントはすぐに削除することが大切です。
5-5 ログの保存や分析
ログの監視も、セキュリティー対策に有効です。いつ誰がどのファイルにアクセスしたのかを把握することで、不正アクセスを受けてしまった場合も、ログを参照してすぐに被害を把握できます。
また、内部で情報漏えいがあった場合も、アクセスログを確認することで個人を特定可能です。
⇒ログ解析ソフトのご紹介いたします。ご相談、お問い合わせはこちら
5-6 セキュリティーパッチの迅速な適用
ソフトウェアの脆弱性や不具合を放置すると、サイバー攻撃を受けるリスクが高くなります。サーバーのOSやソフトウェアは、常に最新の状態に保っておくことが大切です。
脆弱性や不具合を改善するためのセキュリティーパッチ(修正プログラム)が公開された場合は、可能な限りすぐに適用して、脆弱性を解消しておきましょう。
5-7 不要なアプリケーションやサービスの削除
サーバー上で、現在は使用していないサービスやアプリケーションが起動していると、それらの脆弱性を突かれて悪用される恐れがあります。最低限必要なアプリケーションやサービス以外は削除したり、停止したりすることも重要です。
5-8 セキュリティー対策用のシステムの導入
サーバーの設定を変更したり、セキュリティー対策用のサービスを導入したりするのも良い方法です。ファイアウォールやIDS/IPS、WAFを導入し、セキュリティーを保ちましょう。それぞれの特徴は、以下のとおりです。
・ファイアウォール
IPアドレスやポート番号などの情報を確認したうえで、不正なアクセスを制限します。外部からの攻撃を防ぐことが可能です。
・IDS/IPS
外部からの攻撃や不審な通信を検知・ブロックするシステムです。ファイアウォールだけでは不正なアクセスと判断できないサイバー攻撃から、サーバーを守ることができます。
・WAF
Webアプリケーションに対するサイバー攻撃に特化したシステムです。通信内容を確認し、不審な点が見られる時は通信を遮断します。ファイアウォーIDS/IPSでは防ぎきれない攻撃を防ぐことが可能です。
6 トラブルが起きたら専門業者へ相談することが大切

万が一サーバーが攻撃を受けてしまい、情報漏えいや不正アクセスなどが行われた際には、落ち着いて対処することが大切です。
サーバーの記録媒体に対する不正の証拠を調査する場合は、できるだけ早く専門業者に相談してください。具体的には、デジタルフォレンジックサービス業者に依頼することをおすすめします。
7 サーバーセキュリティー対策でリスクを抑えよう
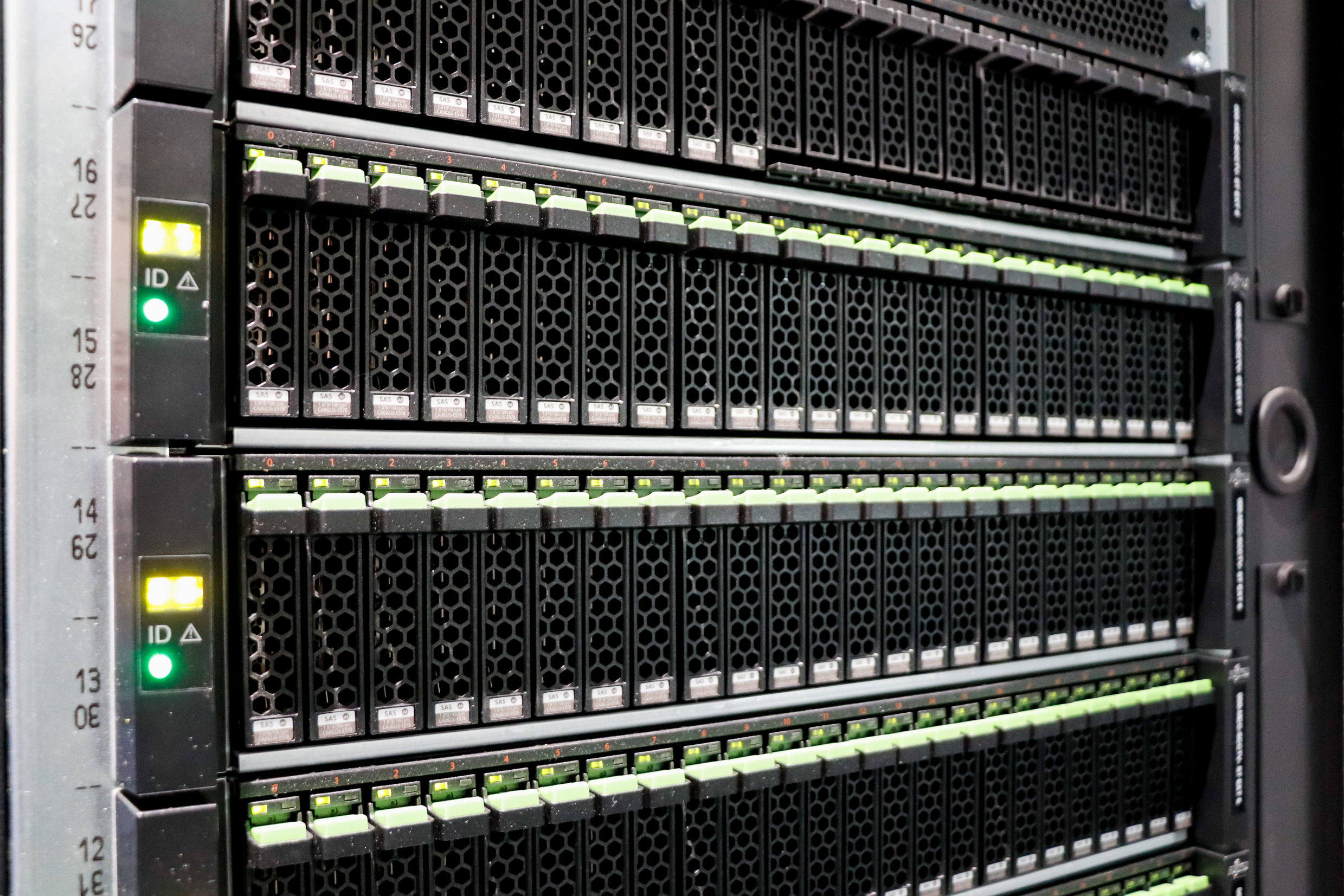
サイバー攻撃の増加などにより、サーバーセキュリティー対策の重要性は高まり続けています。一度でもデータを流出させてしまうと、企業は信用の失墜や損害賠償など、大きな被害を受けます。その後の信用回復に多大な労力が必要になるため、サーバー管理者は日頃から対策をしておくことが重要です。
現状のサーバーセキュリティーに不安を感じている場合は、今回の内容を参考に対策を検討してみてください。